

本ページはプロモーションが含まれています。
おせちの由来とは?なぜ正月に食べるのか、意外と知らないその理由に驚き!
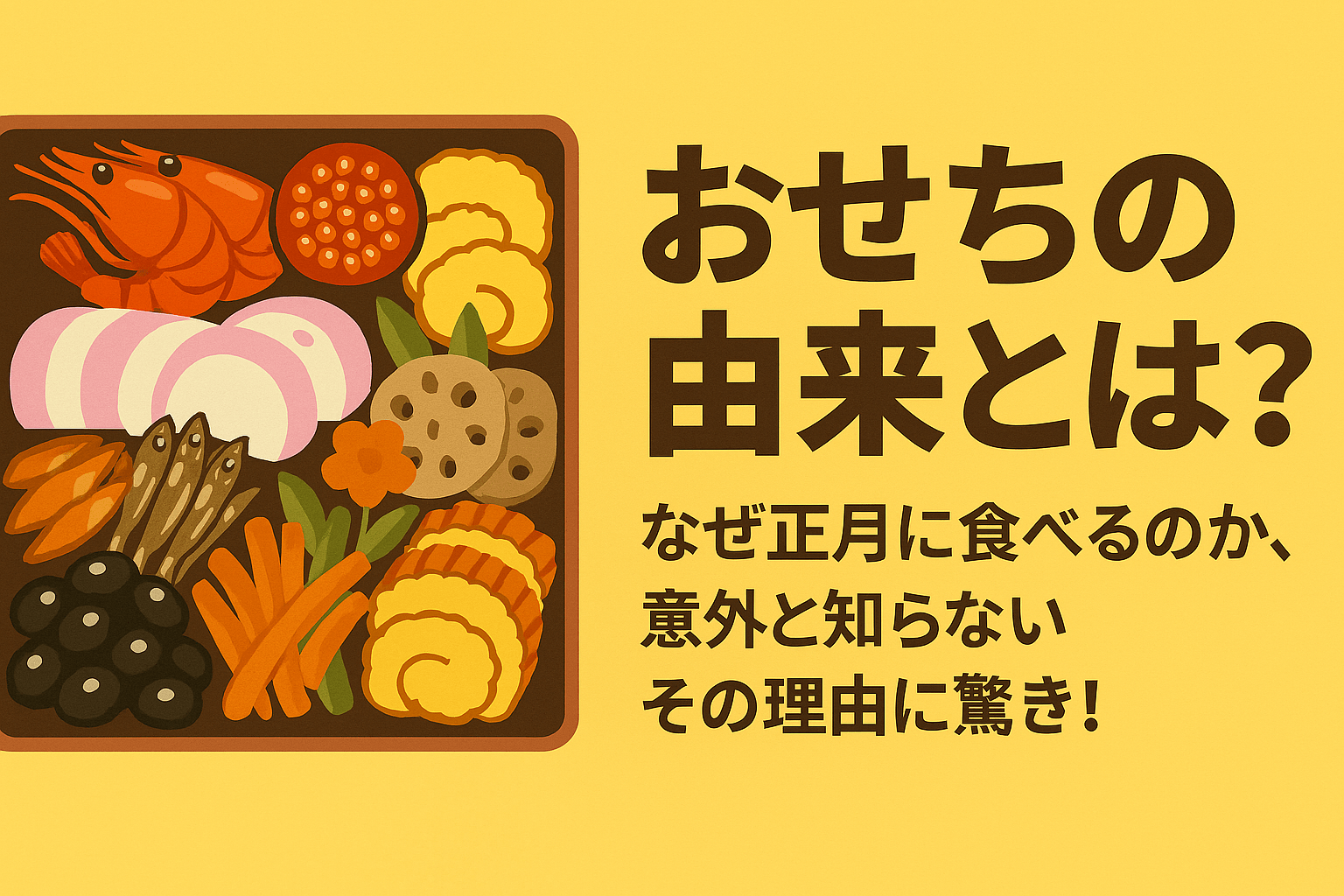
おせちの由来は古代日本の「五節供」にあり、神様に供える「御節供」が起源です。
正月に食べる理由は、家族の健康と繁栄を願い、年始の台所仕事を休むためという実用的な意味もありました。
実は多くの人が知らないおせちの真の意味や、なぜこの時期に重箱に詰めて食べるのかには、日本の歴史と深い文化的背景が隠されています。
現代でも受け継がれるこの伝統の本当の価値を知らずにいるのは、もったいないことです。
弥生時代から現代まで続く、おせち料理に込められた先人たちの知恵と願いを詳しく解説します。
おせち料理の由来と語源
古代から続く「御節供」の歴史と、「おせち」という言葉の本当の意味を探ります。
「おせち」の語源は「御節供」
おせち料理の「おせち」という言葉は、漢字で「御節」と書かれ、「節(せち)」という季節の節目を意味する言葉に由来します。
その起源は日本古来の「五節供」の行事に遡り、元々は神々に感謝する目的で用意された特別な料理である「御節供(おせちく)」が基となっています。
おせちの歴史的起源
おせち料理のルーツは、日本の弥生時代まで遡ります。
農耕文化が日本に根付くにつれて、収穫物を神様へ捧げる儀式が盛んになり、これが特別な料理としての「おせち」の始まりと考えられています。
奈良時代から平安時代にかけて、宮中では「五節供」という重要な行事が行われており、その中で神々や祖先に感謝の意を示すために、豪華な「御節供」という祝宴料理が供えられていました。
これが、現在のおせち文化の原型です。
現在のような形でのおせち料理が確立されたのは江戸時代に入ってからのことです。
この時代には、三が日の間、家庭の主婦が炊事を休めるように保存できる料理を準備するという習慣が生まれました。
なぜ正月におせちを食べるのか
神様への感謝から始まり、家族の願いと主婦の知恵が込められた正月の習慣です。
神様への供物としての意味
おせち料理の起源は、神様に供える儀式で準備される「御節供(おせちく)」にあります。
食卓におせちを並べることで、神様に豊作や家族の健康を願う心が形となり、正月の重要な文化の一部として定着しました。
家族の繁栄と健康を願う象徴
お正月におせち料理を食べることは、家族や親族の繁栄や健康を願う意味が込められています。
おせち料理には、「子孫繁栄」や「豊作祈願」といった願いが込められた食材が多く使用されており、新年を迎える際に縁起を担ぐ料理として重視されています。
年始に台所を休むという知恵
おせち料理は、年始の三が日を「台所仕事を休む日」として過ごすための準備として作られたとも言われています。
これは、年末のうちに炊事を済ませて保存が効く料理を準備し、新年は主婦が家事を休み家族と過ごすための知恵が生んだ風習です。
おせち料理に込められた願いと意味
重箱や食材一つひとつに込められた、縁起と家族への深い願いを解き明かします。
重箱に詰める縁起の意味
おせち料理が重箱に詰められる理由は、幸せが「重なる」という縁起を担ぐ意味があります。
それぞれの段には意味が込められており、一の重には祝い肴や前菜、二の重には魚介類や焼き物、三の重には煮物や野菜などが詰められます。
このように段ごとに料理を詰めることで、新年の繁栄や繁盛を重ねていく心が表れています。
食材に込められた願い
おせち料理に使用される食材には、一つひとつに意味が込められています。
- 黒豆:「まめに働く」「まめに健康で生きる」といった意味が込められ、無病息災を祈る
- 紅白かまぼこ:日の出を象徴し、紅白の組み合わせがめでたさを表す
- 数の子:その見た目から「子孫繁栄」を願う象徴
- 栗きんとん:黄金色をした見た目から「金運」や「財運」を願う
- 伊達巻:巻物の形から知恵や教養を象徴
- 昆布巻:「よろこぶ」という言葉にかけて幸福を祝う
- 田作り:カタクチイワシの幼魚を使った料理で、豊作を願う「五万米(ごまめ)」の名前と小さくても出世するという願いが込められています。
- 海老:髭が長く腰が曲がることから長寿の願いが込められ、赤い色は魔よけの意味もある縁起物です。
- 鯛(たい):「めでたい」の語呂合わせから祝い事に欠かせない魚で、京都では正月三が日は神様への供え物とされます。
- なます:千切り大根と人参の紅白の色合いが水引に見立てられ、縁起が良くさっぱりとした口直しにも最適です。
- 鰤(ぶり):成長に合わせて名前が変わる出世魚で、栄養価も高く出世・健康・長寿を願う縁起物です。
- 小肌栗漬(こはだあわづけ):出世魚の小肌と五穀豊穣を願う黄色い粟を合わせた、縁起の良い酢締め料理です。
- 酢だこ:ゆでると紅白に分かれ「多幸」の当て字から「幸せが多い」という意味で喜ばれる縁起物です。
- 棒鱈(ぼうだら):マダラを完全乾燥させた北海道・東北の保存食で、現在は京都を中心に甘辛く煮て食べられています。
- たたき牛蒡:地中に長く根を張ることから「堅実に暮らす」願いが込められ、関西では「開運」の意味もあります。
地域ごとの特色
日本各地でおせち料理の中身やスタイルには地域独自の特色が見られます。
関東では甘い黒豆やかずのこが主流で、関西では味噌松風やたつくりなど濃い味付けの料理が好まれます。
北陸地方ではブリなどの海の幸を使ったもの、九州地方では甘い醤油を使用した煮物が特徴的です。
それぞれの地方文化や歴史が反映され、多様性豊かなおせち文化が育まれてきました。
まとめ
おせちの由来を知ることで、正月料理の本当の価値が見えてきます。
古代から受け継がれる「御節供」の伝統は、単なる食事ではなく、家族の幸せを願う日本人の心そのものです。
重箱に詰められた一品一品には先人たちの深い願いが込められており、その意味を理解して食べることで、より豊かな正月を迎えることができるでしょう。
現代でもこの素晴らしい文化を大切にし、次の世代へと伝えていきたいものです。